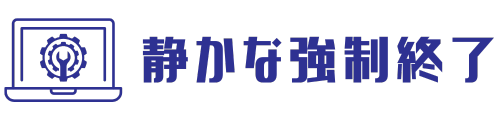「Windows11の評判」は、パソコンを新調したり、アップグレードを検討中の方にとって重要な関心ごとです。
実際に、今使っているWindows10と比べて本当に満足できるのか、不具合や使いにくい点がないかを不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、Windows11のよく挙げられるメリットやデメリット、実際のユーザーの声、ビジネスでの評価まで徹底的に解説し、正直な評判や選び方をお伝えします。
最新の口コミやアップグレード時の注意点まで詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
Windows11の評判を徹底解説

Windows11は2021年に登場して以来、多くのパソコンユーザーから注目を集めています。
新しいデザインや機能、安全性の向上などが話題となり、日常的に利用しているユーザーからの評価はさまざまです。
一方で、従来のWindows10と比較して戸惑いや不満の声も見られます。
ここでは、一般ユーザーからビジネスシーンまで、Windows11の評判について多角的に紹介します。
ユーザー満足度と不満点
Windows11のユーザーの多くは新しいUIや操作感の向上、動作の軽さに満足する声を挙げています。
特に若い世代や最新機種のパソコンを利用している層からは「見た目が洗練された」、「レスポンスが良い」といった好意的な意見が目立ちます。
しかし、その一方で「慣れるのに時間がかかった」、「互換性に問題がある」といった不満も少なくありません。
従来の設定画面や機能の配置が大幅に変わったことで、使い慣れた操作に戻したいという声も多く寄せられています。
よく挙げられるメリットの具体例
- スタートメニューが中央配置になり、操作性が向上した
- ウィジェットやマルチタスク機能が充実した
- セキュリティ機能が強化され、不正アクセス対策が万全になった
- 最新ハードウェアに最適化され、パフォーマンスが高い
- デザインがシンプルで視認性がアップした
パソコンを仕事とプライベートの両方で使う人からは「スナップレイアウト」や「バーチャルデスクトップ」などの便利な機能が評価されています。
また、対応アプリの増加や動作の安定性も、Windows11のメリットとしてよく挙げられています。
主なデメリットや課題
一方で、Windows11にはいくつかのデメリットや課題も存在します。
特に古いパソコンを利用している場合は、システム要件を満たさずアップグレードできないケースが多く報告されています。
また、一部の特殊な周辺機器やアプリケーションが未対応だったり、動作に不具合が出ることもあります。
| デメリット・課題 | 具体的な内容 |
|---|---|
| システム要件の高さ | 古いPCでは導入困難、TPM2.0未対応も問題 |
| 互換性の問題 | 一部アプリや周辺機器が正常に動作しない |
| UIの大幅変更 | 慣れるまで時間がかかる |
| カスタマイズ性の制約 | 従来より自由度が減った設定項目がある |
特にビジネス現場では、導入コストやサポート体制の課題も慎重に評価されています。
アップグレードしたユーザーの声
実際にWindows11にアップグレードしたユーザーからは、「思ったよりスムーズに移行できた」「作業効率が上がった」など、前向きな感想が寄せられています。
一方で、「慣れるまで戸惑った」「古いアプリが使えなくなった」といった正直な声も目立ちます。
SNSや掲示板では「アップデート後、初期設定が手間だった」「使い始めれば快適」と賛否が分かれる意見が見受けられます。
初期不具合の報告もありましたが、アップデートにより徐々に解消されている傾向です。
Windows10との比較による評判
Windows10と比較すると、Windows11はデザインや操作性が大きく変わった点が特徴です。
起動や動作の速さを重視するユーザーには好評ですが、従来の配置や細かなカスタマイズ性を重視するユーザーには賛否が分かれます。
特に業務用途では「Windows10のほうが安定している」との意見も多くみられ、業務の効率や互換性を重んじる環境では移行を慎重に検討するケースが多いです。
一方で、個人利用では新機能やデザイン性が高評価となっており、用途によって評判が大きく分かれています。
各種レビュー・口コミの傾向
IT系メディアやガジェット系YouTuberによるレビューでは、Windows11の進化したUIやセキュリティが高く評価されています。
ネット上の口コミをまとめると、メリットとしては「見た目の美しさ」や「高速な動作」、デメリットとしては「一部古いアプリの動作不可」や「カスタマイズ性の低下」が挙げられます。
また、長くWindowsを利用してきた人ほど、使い勝手への評価が厳しくなる傾向があります。
多くのレビューから総合的に見ると、肯定的な意見も否定的な意見も入り交じる現状です。
企業・ビジネスユーザーの評価
企業やビジネスユーザーにとってWindows11はセキュリティ強化やパフォーマンス向上が大きな魅力とされています。
特にゼロトラスト時代に対応したOSとして、情報システム部門から一定の支持があります。
ただし、社内システムや業務アプリの互換性問題や運用コストの増加を懸念する声も根強く、導入には慎重な姿勢をとる企業も少なくありません。
サポートや更新対応の速さ、端末管理のしやすさも総合的に評価されるポイントです。
Windows11で高く評価されるポイント
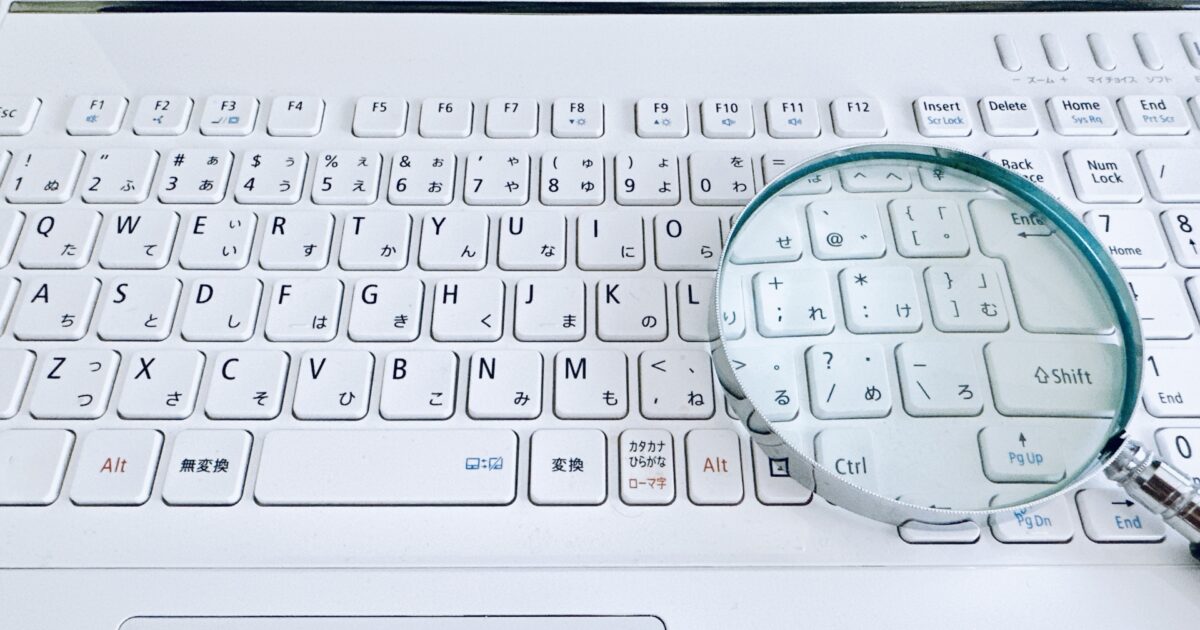
Windows11は、従来のバージョンと比較してさまざまな面で進化を遂げています。
特にデザインや操作性、セキュリティ面、パフォーマンスなど、多くのユーザーから高い評価を受けています。
ここでは、Windows11がどのような点で好評なのかを詳しくご紹介します。
デザイン・操作性の進化
Windows11では、見た目のデザインが大きく刷新されています。
タスクバーやスタートメニューが中央に配置され、よりモダンで洗練された印象になっています。
ウィンドウの角も丸みを帯びており、全体的に柔らかく親しみやすいデザインです。
操作面では、スナップレイアウト機能が追加され、ウィンドウの整理がとても簡単になりました。
- 直感的な操作ができるユーザーインターフェース
- タッチ操作やペン操作にも対応しやすく進化
- 複数のデスクトップをカンタンに切り替え可能
これにより、初めてWindowsに触れる人でも使いやすいとの声が多く上がっています。
セキュリティ機能の強化
Windows11では最新のセキュリティ技術が導入されていることも大きなポイントです。
TPM2.0の必須化やセキュアブートの対応など、高度なセキュリティレベルを実現しています。
これにより、ウイルスやマルウェアからパソコンを守る力が強化されました。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| TPM2.0 | デバイスのセキュリティ強化に不可欠なチップ |
| セキュアブート | 起動時に不正なソフトウェアを防止 |
| Windows Hello | 顔認証や指紋認証による素早いサインイン |
特に、Windows Helloの顔認証や指紋認証によるサインインは、パスワード管理の手間が減るだけでなく、安全性も高いと好評です。
パフォーマンスと安定性
Windows11は、従来のWindows10と比べてもパフォーマンスや安定性が向上しています。
起動やシャットダウンの速度が速くなったという報告が多く、新しいハードウェアとの相性も良好です。
また、最新のDirectXや高効率なメモリ管理により、ゲームやクリエイティブ作業も快適に行えます。
長時間の作業でもシステムが安定して動作する点が、多くのユーザーから支持されています。
Windows11の使いにくい点
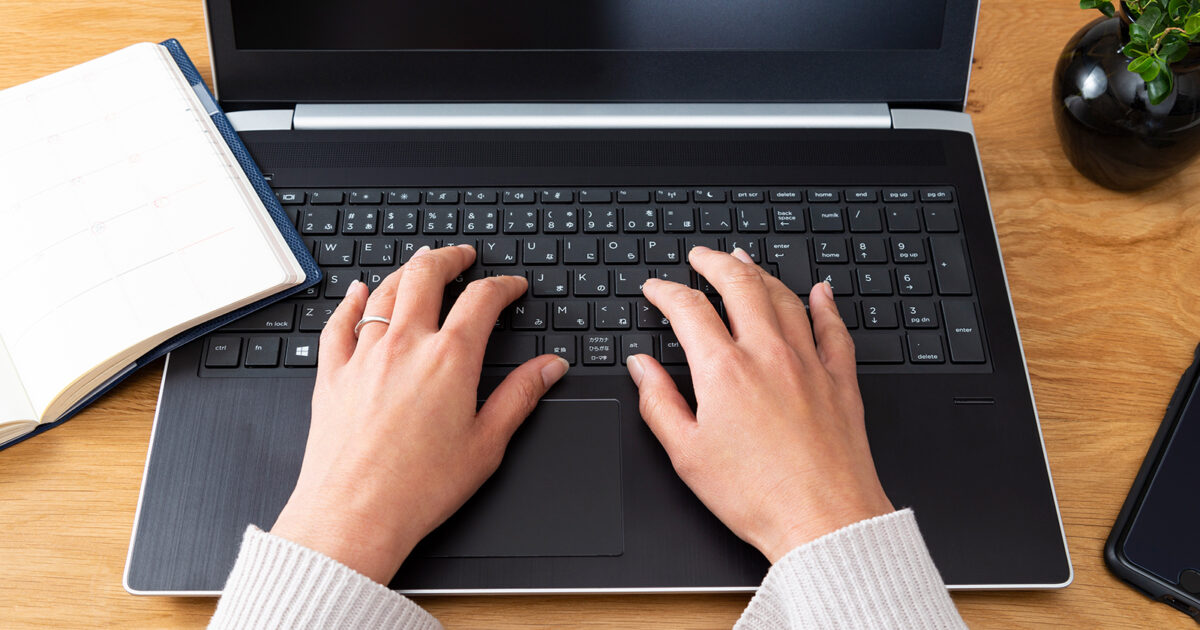
Windows11は最新の機能やデザインが話題となっていますが、一方で使いにくいと感じるポイントも利用者から指摘されています。
特に従来のWindowsと比べて操作方法や設定の変更点が多く、戸惑うユーザーも少なくありません。
ここでは、Windows11が「使いにくい」と感じられる主な理由について解説します。
インターフェースの使いにくさ
Windows11では、スタートメニューやタスクバーのデザインが大きく変更されました。
中央に配置されたスタートボタンは従来の左下配置に慣れている人にとって違和感があり、作業効率の低下を招いています。
- スタートメニューの階層構造が浅くなり、アプリへのアクセス手順が増えた
- 右クリックメニューの項目が簡略化され、慣れた操作がしづらい
- 通知領域や設定画面もデザインが刷新され、機能の場所が分かりにくくなった
これらにより、従来のWindowsを長く使ってきたユーザーほど戸惑いやすい設計になっています。
カスタマイズ性の制限
Windows11では、一部のカスタマイズ機能や設定変更が制限されています。
たとえば、タスクバーの位置が下側に固定され、これまでできていた左右や上側への移動ができなくなりました。
また、既定のブラウザやアプリの切り替え設定も、従来より手順が複雑化しています。
| 設定内容 | Windows10 | Windows11 |
|---|---|---|
| タスクバーの移動 | 上下左右に移動可能 | 下固定のみ |
| 既定ブラウザ変更 | 簡単に切り替え可能 | 拡張子ごとに個別設定が必要 |
| 右クリックメニュー編集 | 自由度が高い | 編集不可(一部項目のみ表示) |
これらの制限により、自分好みに自由にWindowsをカスタマイズしたいユーザーからは不満の声も聞かれます。
対応ハードウェアの厳格化
Windows11の導入には、従来と比べて厳しいハードウェア要件が求められます。
特にTPM 2.0やセキュアブート対応など、セキュリティ重視の仕様が追加されました。
この結果、比較的新しいPCであっても一部の機種ではアップグレードができないケースが発生しています。
また、自作PCや企業の大量導入の際も、対応要件をクリアするための追加コストや手間がかかることがあります。
せっかくパソコン自体は正常でも、OSのアップグレードができずに古いバージョンを使い続けているユーザーも多い現状です。
Windows11で発生しやすい不具合やトラブル
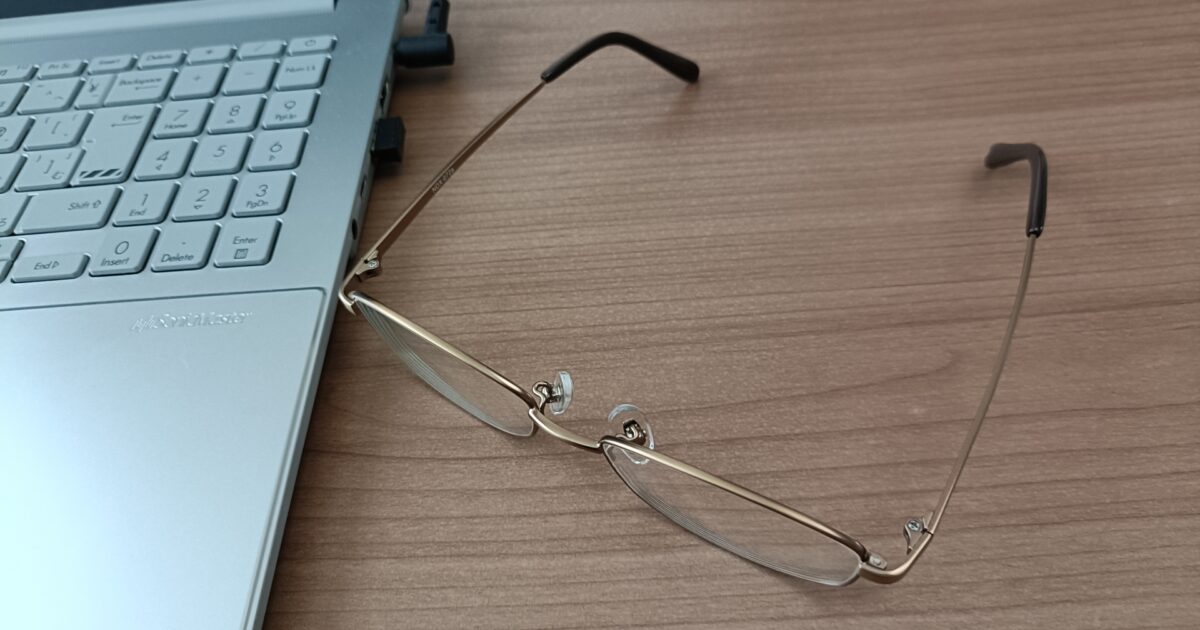
Windows11は多くの新機能やデザイン刷新が話題となっていますが、一方でさまざまな不具合やトラブルも報告されています。
特にアップデートのタイミングや使用しているアプリ、周辺機器によっては予期しない問題が発生することも少なくありません。
ここでは代表的なトラブルについて確認していきましょう。
アップデート後の不具合
Windows11のアップデートは従来のバージョンに比べて頻繁に行われています。
そのため、アップデート直後に動作が不安定になったり、特定の機能が使えなくなったという声が多く見受けられます。
主な不具合例を以下にまとめます。
- 起動時間が遅くなる
- ネットワーク接続が不安定になる
- 一部の設定が初期化される
- 特定のアプリが強制終了する
- ブルースクリーンが発生する
これらは個々の環境やアップデート内容によって生じるケースもあり、公式サポートからの修正パッチを待つ必要がある場合もあります。
アプリ・周辺機器との互換性問題
Windows11の評判に関してよく話題になるのが、アプリや周辺機器との互換性問題です。
新しいOSでは古いアプリケーションや一部のハードウェアが正常に動作しないことがあります。
| 項目 | 主な内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 古いアプリが起動しない | ソフトウェアのバージョンが対応していない | 最新版へのアップデートを検討 |
| プリンターが認識されない | ドライバー未対応 | メーカーHPから最新ドライバを入手 |
| USB機器の接続トラブル | 一部ハードが認識しない | 別ポートの使用・再起動を試す |
特定の業務用ソフトや古いプリンターなど、サポートが終了している場合は特に注意が必要です。
公式サイトで事前に互換性情報を確認することがトラブル回避につながります。
タスクバーやスタートメニューの問題
Windows11ではタスクバーやスタートメニューのデザインが大きく変更されました。
これに伴い、多くのユーザーから使い勝手について賛否の声があがっています。
主なトラブル例には以下のようなものがあります。
- スタートメニューが突然消える・開かなくなる
- タスクバーにアイコンが追加できなくなる
- 通知領域にアプリが表示されない
- カスタマイズ設定が反映されない
このような不具合の多くは、アップデートや一時的なバグが原因になっている場合があります。
再起動や設定の見直しで改善するケースもありますが、根本的な解消には今後のアップデートを待つ必要があるでしょう。
Windows11へのアップグレードを検討する際のポイント

Windows11へのアップグレードを考える際は、ご自身の使い方や現在のパソコン環境に応じて慎重に判断することが重要です。
新しい機能やセキュリティの向上などのメリットだけでなく、これまでのソフトや周辺機器との互換性もチェックしましょう。
スムーズにアップグレードを進めるためには、事前に必要な知識や準備を整えておくと安心です。
アップグレードの推奨環境とタイミング
Windows11へのアップグレードには、一定のハードウェア要件を満たしていることが前提となります。
特にCPUやメモリ、ストレージ容量、TPM2.0対応などが求められるため、ご自身のパソコンの仕様を事前に確認しましょう。
アップグレードのタイミングとしては、以下のような場合が適しています。
- 使っているパソコンが公式のシステム要件を満たしている
- 普段使っているソフトウェアがWindows11に正式対応している
- パソコンの動作やセキュリティ面で、今後のサポートを気にしたい場合
安定した環境で Windows11 を使いたい場合は、アップグレードから数か月経過し初期の不具合やトラブルが解消されてから実施するのもおすすめです。
移行時の注意点
Windows11へ移行する際は、データのバックアップが非常に重要です。
万が一トラブルが発生しても、個人データや大切なファイルを守れるように事前準備をしておきましょう。
| 移行前の準備 | 内容 |
|---|---|
| データのバックアップ | 外付けHDDやクラウドストレージに重要データを保存 |
| ソフト・周辺機器の確認 | 利用中のソフトやプリンター等の対応状況を事前に調べる |
| ライセンスやアカウント情報の控え | 再インストールに必要な情報をメモしておく |
また、すぐに使いたいアプリやデータがある場合は、移行前後での動作確認も忘れずに行いましょう。
アップグレードの際には電源を切らず、作業中はインターネットに安定して接続できる環境を用意するとより安心です。
Windows10を使い続ける場合のリスク
Windows10のサポート終了日が近づくにつれて、セキュリティのリスクが大きくなります。
サポートが終了すると、新たなウイルスやサイバー攻撃に対するセキュリティ更新プログラムが提供されません。
また、最新のアプリケーションやデバイスがWindows10非対応となっていく可能性も高まります。
以下のようなリスクが考えられるため、留意しておきましょう。
- ウイルスやマルウェアなどのサイバー攻撃に対して脆弱になる
- 新しいプリンターや周辺機器がサポートされなくなる
- 最新のソフトウェアやサービスが利用できなくなる
今後も安全・快適にパソコンを利用したい方は、早めにWindows11へのアップグレードを検討することをおすすめします。
Windows11の評判をふまえたオススメの選択肢

ここまで、Windows11の評判や特徴について詳しく見てきました。利用者の声からは、高いパフォーマンスや新しいデザインを評価する意見がある一方で、動作要件や操作性の変更に戸惑う声もありました。
Windows11を選ぶべきかどうかは、ご自身のパソコンの使い方や環境、求める機能に大きく左右されます。もし最新機能やセキュリティの強化を重要視する場合は、アップグレードや新規購入を検討するのが良いでしょう。
ただし、安定した作業環境や対応ソフトとの互換性を重視する場合、Windows10のまま使い続けるという選択肢も間違いではありません。サポート期限や将来的なアップデートも踏まえて、ご自身に合った最適な選択をしてみてください。
この記事を参考に、ご自分の目的やパソコン環境にあったWindowsバージョンを選んで、快適なPCライフにつなげていただければ幸いです。